世界の食料問題を考える日として、国連が制定したのが10月16日の「世界食料デー」。1945年10月16日に創設された国連食糧農業機関(FAQ)は、世界の飢餓問題や食糧課題について、問題解決に向けた行動を促しています。記事では、日本の食に関する問題について、私たちができる具体的なアクションについてご紹介します。
日本における貧困
日本の相対的貧困率は、先進国のなかでも高い水準となっています。「相対的貧困」とは、その国や地域のなかで比較して、大多数よりも貧しい状態のことを指します。背景には、ひとり親家庭の増加や非正規雇用の拡大、高齢化など様々な要因があるとされています。 また、子供の貧困も深刻です。厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2022年公表)によると、2021年の日本の子どもの貧困率は11.5%でした。
日本の貧困問題に対して、行政は生活保護の制度や児童扶養手当、就労支援などをしています。地域や団体による支援は、フードバンクや子ども食堂などがあります。
食品ロスの現状
環境省によると日本の食品ロスは、約464万トン発生しています。(令和5年度の公表)内訳は、事業系食品ロスが231万トン、家庭系食品ロスが233万トンです。家庭系食品ロスについての調査では、食べられるのに捨てられた理由として「食べ残し」「傷んでいた」「賞味期限切れ」と回答が多いことが分かりました。
食品ロスは、食品廃棄時に焼却による二酸化塩素の排出や、焼却後の灰の埋め立てなど環境問題とも切り離せない問題です。また廃棄処理には多額の費用がかかり、不足分は税金で賄われています。
私たちができること
🔶食べ切れる量だけ購入する
買い物をする前に、冷蔵庫をチェックし必要なものだけを購入しましょう。買い物リストのメモを持っていくと、買いすぎ防止になります。腹をすかせて買い物に行くと、買う金額が64%増えるというアメリカの面白い実験結果もありました。
🔶地元食材を買う(地産地消)
食べ物の流通にかかるエネルギーコストを削減できます。そして、新鮮な食材は美味しいですよね。地元の農家さんやお店を応援できるのも嬉しいです。
🔶賞味期限の近づいているもの、見切り品を選ぶ
賞味期限は目安なので、少しすぎでも美味しさは変わらないです。見切り品のコーナーでは、まだ美味しく食べられるお野菜が割引で買えることもあります。賢く、そして地球にもお財布にも優しい選択ができたらいいですね。
🔶フードドライブや寄付活動に参加
フードドライブとは、家庭で余った未使用の食品を回収し、食料に困っている人たちに無償で寄付する活動のことです。自治体やスーパーに食品を持ち寄られた食材は、フードバンクや子ども食堂、生活困窮者支援団体に届けられます。最近、フードドライブに取り組むスーパーが増えていますね。イオンやアークスグループ、ファミリーマートなどに設置されていて、以前よりも寄付のハードルが下がっていると感じています。
🔶フェアトレード商品を選ぶ
フェアトレードとは、開発途上国の生産者が正当な価格で商品を取引できるよう支援する仕組みのことです。生産者や労働者の生活改善や経済的自立の支援につながります。貿易をより公平・公正なものにするための活動であるフェア・トレードに基準が設定され、クリアした製品に国際フェアトレード認証ラベルがついています。

まとめ

10月16日の世界食料デー。食品をロスや貧困問題について関心を持ち、考えるきっかけになったらいいなと思います。ボタンを押せば、お店に入れば、すぐ食べ物が手に入る世の中。当たり前は1つもなく、その裏にはたくさんの人が関わっていて私たちの食を支えてくれています。生産者さんや流通に関わる方、そして美味しい食料が育ってくれる自然への感謝の気持ちを忘れずにいたいです。「いつもよりゆっくり味わって食べる。」「大切な人と食事を楽しむ。」「食べ物が作られる過程を調べてみる。」身近にできることから、是非なにかトライしてみてくださいね。




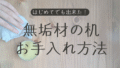
コメント